 ブログ
ブログ 【ブログVol.77】TOC流の製販調整
製販調整(S&OP:Sales and Operations Planning)とは、通常直近の短期間にフォーカスして、何をどれだけ生産し販売するか販売部門と生産部門で調整する、よく知られた慣習です。しかし、見込めるスループット(T)と、残...
 ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ  ブログ
ブログ 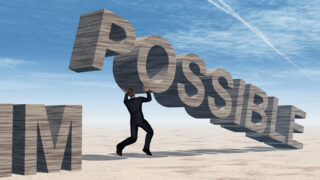 ブログ
ブログ